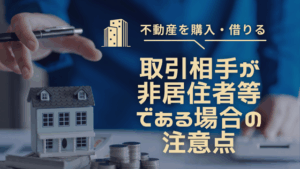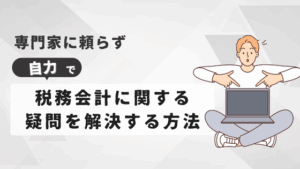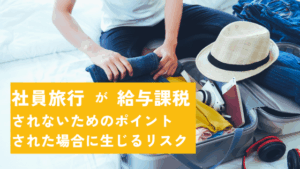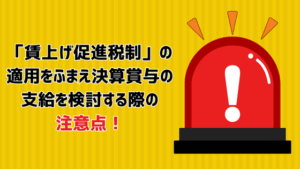ミュージシャンや音楽制作会社など、音楽関連のお仕事をされている場合、仕事道具として「楽器」を購入することは当然あるでしょう。また、音楽関連の事業を行っていない会社だとしても、例えば、店舗のディスプレイ用として「楽器」を購入することがあるかもしれません。
私のような趣味で楽器を弾いている人間は、業務とは無縁な支出なので、「楽器」の購入代金を経費として落とすことはできませんが、業務に関連するものであれば、一部例外を除き、経費として落とせます。
ただ、プロの方々が使用する楽器・機材は高額なケースが多いため、購入時の処理を誤ってしまうと、適切に税負担を減らすことができなかったり、後々痛いしっぺ返し(税務調査での指摘等)を受ける可能性がありますので、「楽器」にまつわる減価償却の基本を、ひと通り、押さえておきましょう!
楽器の購入代金は基本「5年」で分割して経費化する
「楽器」は、基本的には「資産」に該当します。
したがって、購入した年度に、購入代金の全額を一時に経費として落とすのではなく、国税庁が定めた法定耐用年数(『減価償却資産の耐用年数等に関する省令』記載あり)に従い、数年にかかけて分割して経費化します。この処理を「減価償却」といいます。
ちなみに、楽器の法定耐用年数は「5年」(器具及び備品>11前掲のもの以外のもの>楽器)です。
なお、「減価償却」の方法は、「定額法」と「定率法」という2種類がありますが、個人事業主の場合には「定額法」、法人の場合には「定率法」が法定償却方法※となっています。
法定償却方法と違う償却方法にしたい場合は、事前に税務署に「減価償却資産の償却方法の届出書」という書類を提出し、承認を受ける必要があります。
10万円~30万円の価格帯の楽器は「即時償却」「3年均等償却」を選べる
前項にて、楽器は『一度「資産」として計上し、5年かけて経費化する』と記載しましたが、例外の処理方法があります。そのひとつが、比較的、安価な楽器を購入した場合です。具体的には、1組あたり30万円未満の場合、価格帯に応じて、原則とは異なる方法により処理することができます。
| 取得価格 | 償却方法 | 償却資産税 |
|---|---|---|
| 10万円未満 (又は使用可能期間が1年未満) | 「少額の減価償却資産」として即時償却 | 対象外 |
| 10万円以上20万円未満 | 「一括償却資産」として3年均等償却 | 対象外 |
| 10万円以上30万円未満 | 「少額減価償却資産の特例」を適用し即時償却 ※各事業年度300万円が上限 ※資本金1億円以下の中小企業に限る | 対象 |
上記の図は、価格帯ごとの処理方法を一覧にしたものです。
まず、10万円未満の場合は、購入した年度の経費として落としてしまってOKです。会計ソフトに入力するときの勘定科目は「消耗品費」で良いでしょう。
10万円以上20万円未満の場合は、「一括償却資産」として3年間に分割して経費として落とします。この「一括償却資産」として処理した場合、固定資産税(償却資産)※の対象資産からは除かれるというメリットがある反面、3年間の途中で除却等をしてモノ自体がなくなったとしても、3年間は均等償却の処理を続ける必要があります(モノが無いのに償却を続けるのは変に感じるかもしれませんが…)。
10万円以上30万円未満の場合は、青色申告をしていることが条件になりますが、「少額減価償却資産の特例」を適用し、購入した年度の経費として落とすことができます。勘定科目は10万円未満の場合と同様「消耗品費」で構いません。なお、「少額減価償却資産の特例」を適用した資産は、固定資産税(償却資産)※の対象資産になるので、申告モレのないようご注意ください!
10万円以上20万円未満の場合、「一括償却資産」として3年で均等償却するか、「少額減価償却資産の特例」を適用し、購入した年度に全額償却するか選択することができます!
【固定資産税(償却資産)とは?】
固定資産税(償却資産)とは、固定資産税のうち、土地及び家屋以外の事業用資産(構築物、機械装置、工具器具備品など)に対して課される税金で、償却資産を所有している事業者は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容を、都・県税事務所へ申告する必要があります。
なお、税額は「課税標準額×1.4%」ですが、課税標準額が150万円未満の場合には課税されません。
中古で購入した楽器は、たいてい「2年」で償却できる
次は、中古の楽器で購入した場合の処理方法です。
楽器は中古市場が成熟しており、音や希少価値の観点から「中古」だからといって、値崩れしない楽器もたくさんありますが、税務上は、「中古」の資産は、新品で購入したものよりも、使い古されている訳ですから、使用可能期間が短いと考えられます。
そのため、新品の場合「5年」とされる耐用年数も、中古の場合「5年」より短くなります(=早期に経費化できる)。
| 耐用年数 | |
|---|---|
| 法定耐用年数の全部を経過した資産 | その法定耐用年数の20%に相当する年数 【例】経過年数10年の場合 5年×20%=1.0年⇒1年<2年 ∴2年 |
| 法定耐用年数の一部を経過した資産 | その法定耐用年数から経過年数を差引いた年数に 経過年数の20%に相当する年数を加えた年数 【例】経過年数2年の場合 (5年-2年)+2年×20%=3.4年⇒3年 |
基本は、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によりますが、使用可能期間の見積りは困難であることが多いため、実務的には、上記の簡便法により算定した年数を用います。
法定耐用年数の全部を経過した楽器、要は「5年落ち」の楽器の耐用年数は2年です。中古市場で「5年落ち」の楽器はざらにあるので、中古で購入した楽器はたいてい2年で償却できると言って差し支えないでしょう。
【私見】高額なビンテージ楽器の減価償却の可否について
前述のとおり、中古は比較的、早期に経費化できますが、ビンテージ楽器と呼ばれるような、高額な楽器については、経費にするこができないケースもありますので、注意が必要です!
ビンテージ楽器については『「CoCo壱」創業者所有の「ストラディバリウス」の減価償却が認められず約20億円の申告漏れ』となった事例があまりに有名なため、『ビンテージ楽器=減価償却できない』というイメージがあるかもしれまんが、必ずしもそうとは限りません。
| 1点100万円未満 | 1点100万円以上 | |
|---|---|---|
| 原則 | 減価償却資産 | 非減価償却資産 |
| 時の経過によって価値が 減少しないことが明らかなもの | 非減価償却資産 | 非減価償却資産 |
| 時の経過によって価値が 減少することが明らかなもの | 減価償却資産 | 減価償却資産 |
法人施行令第13条「減価償却資産の範囲」、法人税基本通達7-1-1「美術品等についての減価償却資産の判定」、更に「美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ」などを参照すると、「CoCo壱」創業者所有の「ストラディバリウス」の減価償却が認められなかったのは、あくまで「時の経過によりその価値の減少しない資産」とされたためであり、全てのビンテージ楽器の減価償却が否認されるというものではありません。
とはいえ、法人税基本通達7-1-1において、『取得価額が1点100万円以上であるもの(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く。)は、「時の経過によりその価値の減少しない資産」と取り扱う。』と記述があり、中古市場では、ビンテージ楽器の価値が高止まりしている現状を考慮すると、例えばギターやベースで言えば、100万円を優に超えるようなフェンダーやギブソン等のビンテージ楽器について、減価償却費を計上することは厳しいと言わざるを得ません。
ただし、同通達の下線部分にて(~除く。)となっていますので、ビンテージ楽器のオリジナルパーツを現行品に変更した等の理由により、市場価値が落ちたことを証明できる(複数の買取業者に見積をもらう)のであれば、例え、購入時の価格が100万円以上したビンテージ楽器であっても、減価償却することは可能であると考えます。