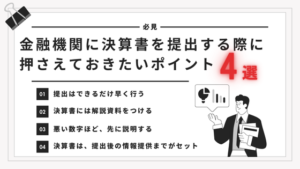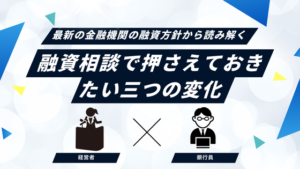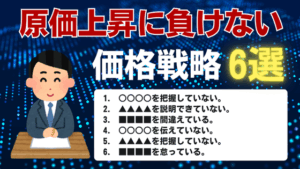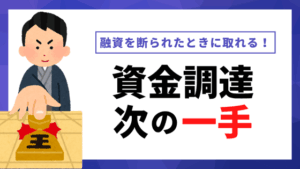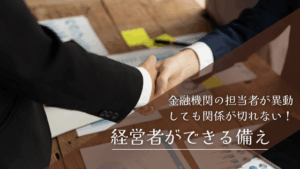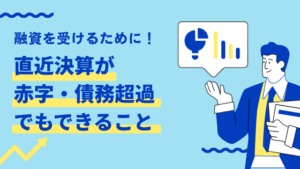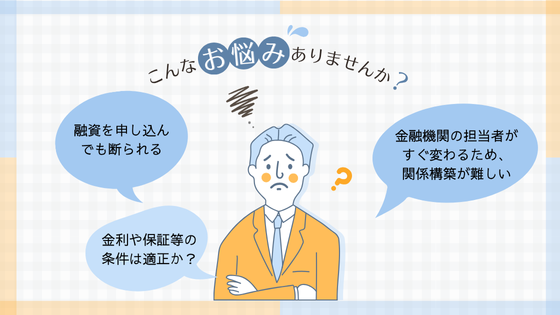
中小企業経営において、金融機関との取引は欠かせません。
しかし、「融資が通らない」「担当者がよく変わる」「経営者保証を外したい」など、多くの経営者が悩みや不安を抱えています。
今回は、経営者からよく寄せられる金融機関取引に関する代表的な悩みを取り上げ、それぞれの背景と具体的な対応策をまとめました。
悩み❶「融資を申し込んでも断られる」
悩み❶+その背景
最近、「融資を申し込んでも断られる」という相談が増えています。
この背景には、2024年4月に改正された金融庁の「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の影響があり、各金融機関が融資審査をより慎重に行うようになっていることが挙げられます。
特に、財務内容が悪化している企業に対しては、融資が通りにくい傾向が強まっています。
対応策❶「日頃から、事業計画書等を整え、金融機関との関係を密にする」
こうした状況で融資を通すためには、資金の使い道や返済の見通しを具体的に示した事業計画書の提出が不可欠です。
また、日頃から金融機関とのコミュニケーションを密にしておくことで、財務内容だけでは判断できない企業の強みや改善意欲を、担当者が内部で補足説明してくれることもあります。
そのためには、資金繰り表や月次試算表を整え、毎月の業況を自ら説明する習慣が重要です。
さらに、士業やコンサルタントが同席することで、客観的な信頼性が加わり、金融機関側の安心材料にもなります。
悩み❷「金融機関の担当者がすぐ変わるため、関係構築が難しい」
悩み❷+その背景
金融機関では定期的に人事異動があり、担当者が数年以内に交代するのが一般的です。
そのたびに、これまでの取引経緯や信頼関係がうまく引き継がれず、経営者が「また一から説明しなければならない」「ゼロから関係を築き直さなければならない」と感じるケースは少なくありません。
対応策❷「新任の担当者に自社の事業計画書を最初に渡す」
こうした負担を軽減するために有効なのが、新任の担当者に自社の事業計画書を最初に渡すことです。
新任担当者は、前任者からの引き継ぎ内容が限定的であったり、企業の背景を十分に把握していないことも多いため、事業計画書を通じて経営方針や将来の展望、資金の使途などを明確に伝えることが、理解と信頼の第一歩になります。
さらに、窓口を特定の担当者だけに限定せず、支店長や渉外担当役席、貸付担当役席など複数の関係者とも関係を築いておくことで、情報共有の体制が整い、担当者が異動した後も、継続的な信頼関係を維持しやすくなります。
悩み❸「金利や保証等の条件が適正かどうか判断できない」
悩み❸+その背景
融資を受ける際、「この金利は高いのでは?」「本当に経営者保証は必要なのか?」と感じながらも、内容を十分に確認しないまま進んでしまう経営者は少なくありません。
その原因は、条件が妥当かどうか判断できる材料が乏しく、他の選択肢との比較もできていないことにあります。
金融機関に率直に質問しても、担当者が制度に詳しくなかったり、社内方針で具体的な説明を避けられることもあるため、納得感が得られないまま話が進むケースも多く見られます。
対応策❸「専門的な第三者の意見を事前に取り入れる」
正式に申し込む前の段階で、他の金融機関にも相談し、条件や対応方針の違いを比較することが大切です。
また、融資制度に詳しいコンサルタントや支援実績のある士業など、専門的な第三者の意見を事前に取り入れることで、金融機関とのやりとりにも自信をもって臨めます。
急がず、比較と相談のプロセスを踏むことが、納得のいく金融取引への近道になります。